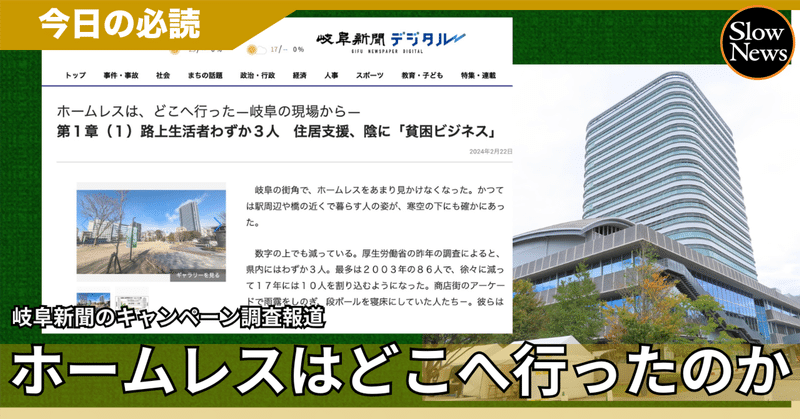存亡を賭けた事態に直面している伝統的メディアと、プラットフォーマーなどの新興メディア。それぞれが抱える様々な問題や、新たな取り組みについての報道をまとめています。(ジャニーズとメ…
- 運営しているクリエイター
記事一覧

メディアや企業の公式アカウントは信頼されない?タテ型動画の最新事情、キーワードは「クリエイター」と「個人」【InterBEE 2024リポート②】
日本最大級のメディア総合イベント「InterBEE」。メディアの最新事情を知ることができるセッションの中から、注目の内容をリポートしています。 今回は、流行りのタテ型動画と「個人メディア化」への最新事情について語られたセッションの内容をご紹介します。 スローニュース 熊田安伸 タテ型動画の最新事情はSNSで急成長しているタテ型動画のトレンドや、マーケティング活用法はどのようなものか。「タテ型動画マーケティングの最前線」というセッションには、プラットフォーマーと広告会社の

10代の若者によるメディア利用の劇的な変化と、予想外の新たな利用時間帯のトレンドとは【InterBEE 2024リポート①】
日本最大級のメディア総合イベント「InterBEE」。今年も昨日(11月13日)から3日間の日程でスタートしました。テレビの放送技術の展示会だと思われがちですが、それだけではありません。メディアの最新事情を知ることができる数十コマに及ぶセッションが開かれるのです。幕張メッセの会場に行けない人のために、注目の内容をリポートしていきます。 まずは、若者を中心に驚くようなユーザー行動の変化がありましたので、そちらから紹介します。彼らに見てもらえる新たな時間帯の傾向とは。 スロー