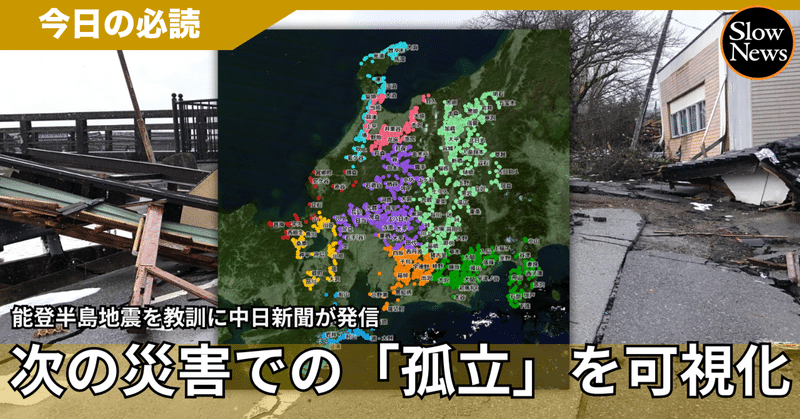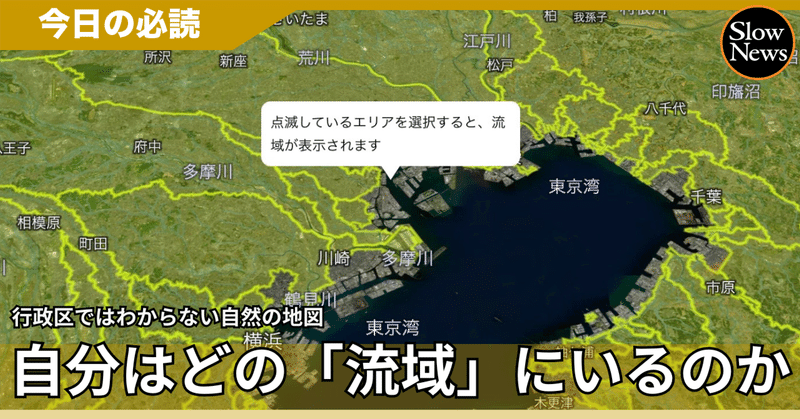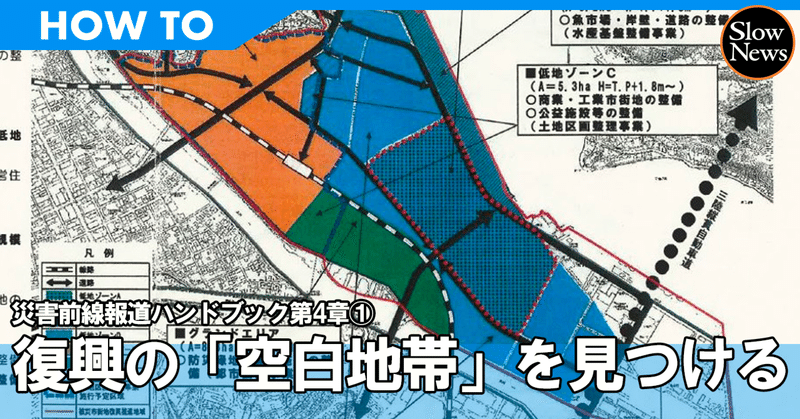大災害は突然にやってきます。その時、何を取材するべきでしょうか。記者たちに的確な指示が出せるでしょうか。ありそうで存在していなかった「災害時の取材マニュアル」ジャーナリストのプレ…
- 運営しているクリエイター
記事一覧

復興支援に投じられた補助金、誰がどう使ったのか、不正はなかったのかを調べる『災害前線報道ハンドブック』第4章 復興フェイズ⑥
スローニュース 熊田安伸 お待たせしました、連載再開です。引き続き、復興フェイズで役立つ取材手法をご紹介していきます。 前回は復旧・復興工事に携わる企業の調べ方をお伝えしましたが、今回はそうした業者などに、どのような補助金が投じられているかを調べる方法を解説します。 自治体の補助金は「主要な施策の成果報告書」から地方自治法に基づいて、地方自治体が決算とともに議会に示すのが「主要な施策(政策)の成果報告書(説明書)」という書類です。年に1度しか出てきませんが、自治体がどん