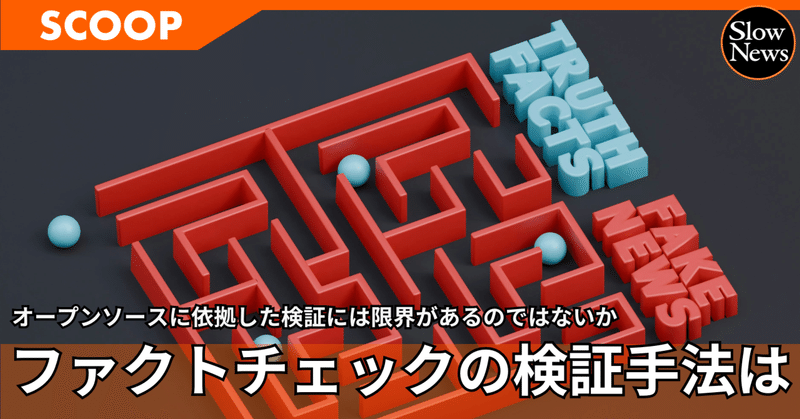
ファクトチェックの「検証手法」を検証する…公的機関のオープンソースに頼る手法の限界
日本最大のファクトチェック機関、「日本ファクトチェックセンター」(JFC)が、国際ファクトチェックネットワーク(IFCN)に加盟してから、この5月末でちょうど1年になる。IFCNの認証は、当初は1年ごとに更新することになっており、JFCも現在、更新審査が進行中だ。
IFCNの事情に詳しい関係者によれば、更新では、これまでのファクトチェックの内容が審査の重要なポイントになるという。
フロントラインプレス
ファクトチェックに求められるポイントとは
IFCNの審査基準によれば、まず、「(申請者による)ファクト・チェックの少なくとも75%は、個人、一般市民、社会の福祉や福利に関連する、あるいは影響を及ぼす可能性のある問題に関連するクレームに焦点を当てている」ことを求めている。また、非党派制や公平性はもちろん、複数の資料を当たること、可能な限り主張を行った人に取材をして裏付けとなる証拠を求めるよう努めることなど、検証の手法にも言及している(ただ、ネット上での主張の場合は、発信者に連絡が難しい場合があると付け加えている)。
ポイントは複数の資料や関係者に取材し、ファクトチェックの質を高める点にある。何が事実かを確認するのは、それ自体が取材であり、事案が複雑な場合には深い取材も必要になる。ファクトチェック自体が調査報道だ。
例えば、AP通信社(米国)の「APファクトチェック」がIFCNに提出した認証更新のための審査資料によると、ファクトチェックの実例として示した14件のうち、真偽の判断基準は13件が「事実関係取材」だった。オープンデータの参照だけで真偽を判定したのは1件しかない。
事実関係取材も1件につき「当事者」「第三者」「専門家」など相手は多岐に及ぶ。トランプ元大統領の子息による投稿の真偽を確かめる際には、当人に取材。フェイク画像が拡散された際には、元をたどり、なぜ拡散が起きたのかの道筋も明らかにした。まさに調査報道だ。

では、国内に3つあるファクトチェック団体のうち、他の2団体を引き離して最も多数のファクトチェック記事を配信している日本ファクトチェックセンター(JFC)はどうだろうか。
公開されているファクトチェック第1号は、2022年9月28日の「『北朝鮮軍がアメリカ人気バンドの曲を演奏』は誤り」。それ以降、100件目までのファクトチェック記事を時系列に並べたものが別表である。それぞれの記事ごとに、真偽の判断基準が何であったか、関係者取材が行われたかどうかも示した(一部に判別不能のものもある)。
一覧表の中では、例えば、「『ヨーロッパでは新型コロナワクチンで死亡しても生命保険は出ない』という投稿は誤り」(2022年11月14日)は、欧州保険協会などに直接取材したものだ。
「『選択夫婦別姓制度が適用されると、名字の異なる人が増えて郵便配達に支障がある』は誤り」(2023年4月17日)は、日本郵便や内閣府に取材し、投稿者本人にも問い合せ。「『三重県南東沖で起きた地震は人工地震』は誤り」(2023年1月11日)のように、荒唐無稽な内容であると容易に判断できる投稿についても、東京大学地震研究所に取材をかけたうえで、「誤り」と判定している。
こうしたファクトチェックが行われている一方で、JFCのファクトチェックには当事者・関係者取材が乏しく、公開データの参照のみで真偽を判断するものも目立つ。
報道機関を検証対象から除外
日本ファクトチェックセンター(JFC)が公表しているこれまでの実績によれば、JFCは旗揚げから2023年12月までの1年3カ月で、200本以上の検証記事を出している。内訳は、新型コロナの関係から医療・健康が最も多く、次に国際関係、政治関係などが並ぶ。
JFCの古田大輔編集長は、検証対象をどのように選んでいるのかについて、「ソーシャル・リスニング・ツールなどを使って、どの程度拡散しているのかを調べたり、影響する人員の広さ、深刻度、主に日本のユーザーにとっての近さという『広さ、深さ、近さ』の三軸の基準で選んだりしている」と取材のなかで説明した。

ただ、JFCのファクトチェックガイドライン(2022年9月)によれば、「正確で公正な言説により報道の使命を果たすことを目指す報道機関として運営委員会が認める者が発信した言説ではないこと」(第19条1項の4)として、大手メディアの報じたニュースはファクトチェックの対象から除外されている。
ガイドラインを策定したのは、JFCの「運営委員会」であり、委員の任免権はJFCを運営する一般社団法人・セーファーインターネット協会(SIA)側にある。
協会の吉田奨・専務理事(JFCの事務局長を兼務)は大手メディアを除外した理由について、「メディアは、例えばテレビなら放送倫理・番組向上機構(BPO)のように自律的な検証機能を持っている。自ら襟を正してやってきているので、まずはそれに委ねる」と説明した。
一方、古田編集長は、「個人的には報道機関も検証対象にすべきだと(内部で)主張していて、設立当初から運営委員会の議題に挙げている」と言及。「納得はいってないが、編集長の一存ですべてが決まるというのもガバナンスとしてはおかしい。仕方ない部分はある」と付け加えた。
JFCの運営委員会(委員長=曽我部真裕・京都大学大学院法科研究科教授)は、非公開で開催されており、議事内容は公開されていない。
原発事故の検証はどのように行われたか
日本ファクトチェックセンター(JFC)は、どのようなかたちで言説をチェックしてきたのだろうか。ここでは検証結果ではなく、検証の手法に着目して見ていきたい。
ここから先は会員限定です。ファクトチェックの検証方法とはどのようにあるべきなのか。

